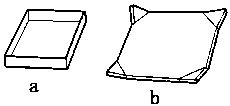第15節 茶懐石料理の沿革
【通解】茶懐石料理の沿革
- さて、古くから、寺院では、獣肉、魚、鳥をさけた料理がつくられてはいたが、精進料理として確立を見たのは、鎌倉時代の禅宗においてであった。
これには、道元禅師の功績も大きかった。
この料理は、禅宗とともに、中国から輸入されたものであったが、その禅宗とともに、日本的なものとなった。
- 禅僧は、修業中、寒さと空腹を、少しでもいやし、胃をひやさないように、温石(おんじゃく)、すなわち、石を僧衣の中の帯の上に置いていた。
これから、懐石(かいせき )と申せば、禅僧を指した。
で、この禅僧が作り、喫食する精進料理を、一名、「懐石料理」とも呼んだ。
(こん日の茶懐石料理と異なる )
この懐石料理は、こん日の精進料理と同じく、植物性蛋白質と、植物性脂肪を多く含むものである。
- 茶は、唐の時代から、中国で、禅宗と結びつき、平安末期に、日本に禅宗の入ったとき、それをもたらした人物、栄西の手によって、「茶の種」も輸入された。
それ以来、日本でも、禅と茶の湯は不可分の関係を持って進んできた。
- で、千利休は、茶道の会合に供する懐石料理ということで、「茶懐石料理」をつくり出した。
このものは、禅門本来の懐石料理(精進料理)の心持ちを、さらに、いっそう追求し、いっそう、枯淡を愛し、自然の風味を愛するものであったと同時に、いっさいの格式をも去ろうとするものであった。
- つまり、狭い茶室や侘び茶が、広間をとり、手間ひまのかかる華美な本膳料理を1つの方向に変え、一汁三菜の簡素な侘びを主体とした料理を作りだしたわけである。
- このように、茶懐石というのは、室町時代、中国から茶道とともに、禅宗の心が入り、新しい禅宗風の食事のしかたが確立したものである。
しかし、茶懐石料理は、日本に育ったので、いくばく本膳料理の影をやどしている。
- 最初に出される「向付け」、「汁」、「飯」は、本膳に相応し、次の椀盛、焼物以下の料理は、二の膳に当たると考えられる。
- また、禅宗の影響を多分に受け、禅僧が托鉢(たくはつ)の途中、食事をするときに使う、鉢単(はったん)と呼ぶ堅い油紙は、折敷(おしき )と呼ぶ足のない平膳のもとになった。
また、使われる食器は、こん日でも、禅僧が常用している飯碗と汁椀とがひとつになる、応量器(自分の食べ量に応じて器の大きさが違う )と呼ばれる食器を参考にしたものである。
喫茶、喫食の心構えは、禅の真髄を求めて修業する僧堂での座禅生活となんら変わりないとするものであった。
- 現在の茶懐石料理には、ある面において、西洋料理の影響が見られる。
前菜、汁物、最後に後甘というように一品ずつ料理が出される点がそれである。
これは、江戸時代初期にオランダの影響をうけ確立されたものである。
- 茶懐石料理と宴会料理の、もっとも大きな違いは、「宴会料理は、食前に、酒と何品かの肴を出される」が、「茶懐石料理は、はじめから、ご飯と汁が出てきて、そのあい間に酒がつがれる」ことである。
- 宴会料理の場合は、どちらかと言えば、酒をおいしく飲むための料理である。
そのため、ご飯は、最後に漬けものでということになる。
- 茶懐石料理は、その点、はじめから食事のテンポに合わせて、次々と料理そのものを味わえるように考えられている。
- 客をもてなすということは、なかなか、むずかしいことである。
おいしい料理を作ってもてなすことは言うまでもない。
が、客のもてなしとは、それだけでない。おいしい料理を作って、もてなす上で大切なことは、その料理を運ぶ「間」である。
膳を運び出して、給仕口のふすまを閉め、次に、ふたたび、ふすまを開ける。
その間の呼吸、これが「間」である。そののち、酒、煮もの、焼ものと続くが、その間の微妙な間に神経を集中しなければならない。
間が早すぎても、店をせわしくし、客を追いたててしまう。
また、間があきすぎても、席をだれさせる。その「間」ということは、実に、大切なことである。
- 四季おりおりの旬の材料だけで献立を作り、季節感を盛り上げると同時に、材料の持つ色、形、香り、味を重んじて、これを素直に生かす。
そして、切れ端まで、けっして、粗末に扱わない簡素な心を厳しく守る態度、季節の寒暖にかかわらず、「温かい料理は、あくまでも温かく」、「冷たいものは、それを盛る器まで十分に冷たくして供する」、こうした心がまえ、心くばりは、家庭料理や専門料理の中でも、大いに、見習わなければならない。
- 茶は、季節の移り変わりを厳しくとらえている。“ 4月、5月は、炉から風炉への時期”“10月は、風炉の名残(なごり)の月”“11月は、炉開き”と、茶懐石の献立の上にも、この季節をはっきり選び分けることが、大切である。
- 茶懐石料理の献立は、海、山、里の幸を重複しないように組み合わせて、それを、できるだけ質の異なるものを組み入れて構成する。
野菜もの、根のもの、軸のもの、茎のもの、葉のもの、実のものなどを、1種ずつそろえる。およそ、植物性と動物性のもの半々くらいで構成するのが、理想である。
- 食べにくいものには、隠し包丁を入れ、骨のあるものは、丁ねいに、骨を取りのぞいておく。
また、たくあんのように、かむ音のはっきり出るようなものは、細かく包丁を入れておくなどの心くばりを忘れないこと。
それが、もてなしの真髄なのである。
- また、料理の着物ともいうべき食器の取り合わせにいたっては、細心の心くばりを必要とすることは、言うまでもない。
【型1】茶懐石料理の出される順序
- 一汁三菜(飯、汁、向付け、煮物、焼物)が基本で、まず、「飯」、「汁」、「向付け」が折敷でだされる。
- 一口、ご飯を食べ、味噌仕立ての汁を音をたてて吸いきったところで、それを合図に主人から酒がすすめられる。
- 酒を飲んでから、「向付け」に手をつける。
- さらに、「煮物」、人数分が一鉢に盛り込まれた「焼物」が出される。
- 「鉢肴(はちざかな)」、「強肴(しいざかな)」といって献立以外の料理を出す場合もある。
- 「小吸物」、「八寸」が出され、客が下戸であれば、「八寸」からあとには、何も出さない。
- 献酬のあと「湯桶(ゆとう )」と香の物がでて食べ終わる。
- 懐紙で膳に落ちた、しずくを押さえて、折敷の上を整え、一同で折敷の縁に掛けてあった箸を折敷の中に落とし、終了の合図をして終える。
- そのあと、菓子と濃茶が供せられる。
【説明】
- 向付け(むこうづけ)……折敷の向こう側に置かれるので、向付けの名称がある。
白身魚の刺身、なます、和え物などを用いる。
昔、冬は刺身、夏は酢の物を出したが、現在では、刺身が主である。
- 煮物……椀盛りとも呼ばれ、茶懐石料理の主役。
魚、鳥、野菜などが中身のすまし汁。
まず、汁を一口味わってから中身を食べる。
- 小吸物……味の薄い、さっぱりした吸物で、小さな椀で出される。
「箸洗」ともいって、これで箸先を洗い、口中をあらたにして、次に出される八寸での献酬を迎える。
- 八寸(はっすん)……約20cm角の正方形の盆のことで、魚介類のなまぐさものと野菜を盛り合わせたり、山海の珍味を数種取り合わせたもので、小吸物の蓋などに取っていただく。
- 湯桶(ゆとう )……つぎ口と横手がついた湯次(ゆつぎ)の湯の子すくいが添えられている。
うすい重湯に塩味をきかせてある。
- 鉢肴(はちざかな)……ご飯のおかずとして出される、たき合わせや酢の物などで、客に預けるので「預け鉢」ともいう。
- 強肴(しいざかな)……強いるので強肴といわれ 進めるので「進め肴」ともいう。
酒が進むように酢の物、おひたし、うに、塩辛の類(酒盗という)を少量出す。
【参考】
正式な茶懐石料理は、「正午の茶事」といって、正午に一汁三菜の茶懐石料理を出すものである。
夏の暑さを避け、朝の涼しい短い時間を利用した「朝茶」や、冬の夜長を利用して、日没後に客を招き、夜半ごろまでに終える「夜咄(よばなし)の茶事」の場合は、一汁二菜が普通である。
一汁二菜は、一汁三菜の中から焼物を省いたものである。
【型2】折敷(おしき)について
a は、略式の場合
b は、正式な茶懐石で用いられる折敷の1つである。
【参考】
茶懐石では、汚れを器に残さないのが作法であるから、魚の骨などは、懐紙に包んで持ち帰られよ。
【型3】
明治時代は、料理を作るとき、ろうそくを灯りとした。
また、材料も、現在のように豊富でなかったので、質素な、本来の茶懐石料理の献立内容であった。
しかし、大正時代になると、電灯を使用するようになり、また、外国からも、多量の肉、その他の山海の珍味が入荷するようになり、次第に、現在のような豪華絢爛たる茶懐石料理になったが、一汁三菜が基本であることには、かわりない。
第6章 和式作法